第49回 断頭台の露から223年(フランス)
2003年、夏のパリ。
フランス政府の「女性の権利と平等に関する事務所」の応接間に通された私の目に、オランプ・ドゥ・グージュのポスターが飛びこんできた。なんと、パリまでの飛行機の中で読み終えた本の主人公だった。
オランプは名、ドゥ・グージュは姓。フランス革命の魂である『人権宣言』(1789)を「男性の権利をうたったにすぎない」と痛罵した女性として知られる。批判だけでなかった。「女性および市民の権利」と称する『女権宣言』を自ら書きおろした(1791)。
その中でオランプは「女性は断頭台にのぼる権利を持っているのだから、演壇にのぼる権利をも有する」と政治への参画を高らかに宣言した。結婚して子どもを産み、家族の世話やしつけにいそしむことが、あるべき女性の姿だった時代の話だ。
王妃マリー・アントワネットに直訴した彼女は「反革命派」のレッテルを貼られた。へこたれることなく、次にロベスピエールの暴力主義を非難した。
そして彼の手にかかって投獄され、1793年11月3日、断頭台の露と消えた。
彼女は、1748年、モントーバンの肉屋の娘として生まれ、18歳ごろに結婚し、20歳で“未亡人”(彼女はこの言葉を嫌った)となった。
まともな教育を受けていなかったので、パリに出てからフランス語を学んだ。投獄されるまでに、何十冊もの戯曲や小説のほか、おびただしい数の政治関係著作を残した。
テーマは、“未亡人”の権利、婚外子の権利、黒人の権利、表現の自由、貧者の連帯、刑事法廷の市民による陪審制、死刑の廃止、所得税の義務など、21世紀の今でも通用するものばかりだ。
「このポスターは、何十倍にも拡大して、2002年3月、『フランスの偉大な女たち』と題したイベントで、パンテオンを飾ったんですよ。マリー・キュリー、シモーヌ・ドゥ・ボーボワールたちと共にね」と事務所所長は私に語った。
フランスには、「偉人が葬られるパンテオンはなぜ男ばかりなのか」という女性運動がある。そこに祀られるべき女性の筆頭がオランプ・ドゥ・グージュだとか。
2016年10月、フランスからこんなニュースが届いた。
「オランプ・ドゥ・グージュのパンテオン入りはなりませんでした。でも、フランス女性たちは、国会議事堂内に彼女の胸像を設置させました。彼女がギロチンにかかってから、実に223年です」
2017年8月10・25日


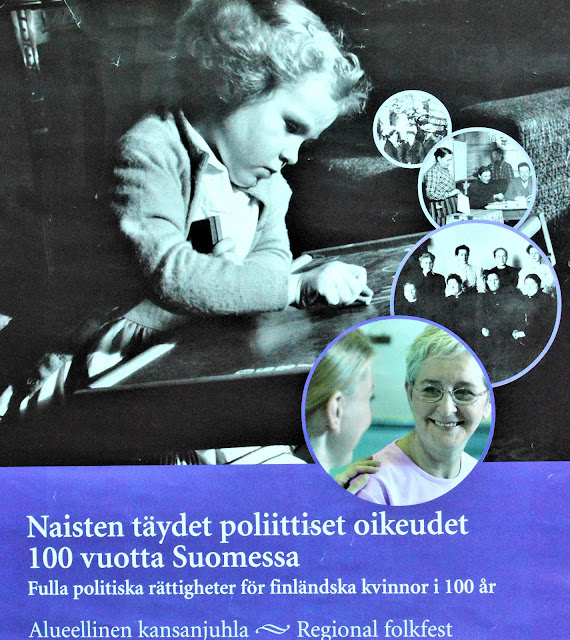

コメント
コメントを投稿