第43回 さあ、一緒に行こう!(スウェーデン)
深い闇に包まれた白い大理石の像。赤い手書きのNU GÅR VI! は「さあ、行こう!」。
これは、1975年に国際女性年を記念して行なわれたスウェーデンのポスターコンテスト優勝作品だ。スウェーデン政府が募集した。女性差別撤廃の運動をもりあげるためだった。作者は美術教師のイヴォンヌ・クラソン。
女性像2体が、ギリシャ神殿の上部を支えている。屋根を支えるために使われた人柱で、カリアティードと呼ばれる。
この絵は、アクロポリスの丘に建つエレクティオン神殿の有名な6体の一部だろう。神殿は、紀元前5世紀末にアテネの王を祭るために造られた。
よく見ると、後のカリアティードは、手前のカリアティードの肩に右手をのせている。「ねえ、一緒に逃げようよ」と誘っているかのようだ。ギョロリと上に向けた目は「頭が重くてかなわないなぁ」と言いたげだ。誘われたカリアティードの目は、遥かかなたを見つめていて、別天地に行きたがっているようだ。
きっと2人は、一晩考えて、アクロポリスの丘から脱走したに違いない。行き着いた先はエーゲ海か、はたまたメキシコの第1回世界女性会議場か。
1960年代から70年代、女性たちは、家庭や職場から屈辱的生き方を押しつけられたり、メディアが女性の性の商品化を煽ったり、女性抜きで物事が決められたりすることに、大ブーイングの声をあげた。
世界に吹き荒れた運動は国連をも動かし、国連は「1975年を女性年」と決め、世界女性会議を開いた。これが後の女性差別撤廃条約の制定になった。
1975年は私にも忘れられない年だった。「国際婦人年をきっかけとして行動を起こす女たちの会」に入会した。TVコマーシャル「わたしつくる人、ぼく食べる人」への抗議の輪に加わった。
教員だった私は、教科書の描写や表現を洗い出して、出版社に改善を要求した。高校入学定員の男女差をやめて成績順にせよと、各都道府県に申し入れた。女生徒のみの必修科目だった家庭科を男女とものカリキュラムに変えるよう要求した。一方、日本政府は世界の動きを尻目に「家庭基盤の充実政策」なる代物まで発表した。保育所充実には目もくれず、家事に専念する主婦が有利となる税制に変えた。洗い出すときりがなくて、まるでモグラ叩きだった。
最近、ポスターの作者イヴォンヌ・クラソンによる「首相と外相への公開質問状」がスウェーデン紙に載った。NATO非加盟にもかかわらずNATO友好国ぶった動きをする政府への反論だった。彼女は「さあ、行こう!」と抗議デモを呼びかけていた。
2017年2月10日


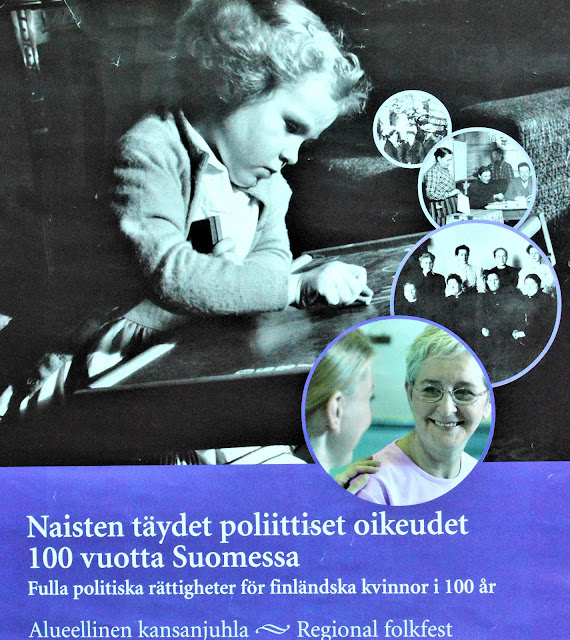

コメント
コメントを投稿